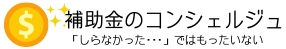最近、企業のクラウド化が大変進んでいます。
クラウド化するメリットは確かにありますが、それらが全てプラスをもたらすかは別問題です。
まずは、クラウド化のメリット・デメリットを正しく把握しましょう。
クラウド化?補助金??
色々な紹介ページがありますが、わかりづらい用語が多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
コロナの緊急事態宣言や働き方改革のため、社外から会社のシステムにアクセスして業務を行うワークスタイル、テレワーク。
テレワークを実現するために、クラウド化を進める企業が増えていますが、実際は、いまいちメリットがわからなくて行動に踏み切れない経営者の方もいらっしゃいます。
そこで、クラウド化するメリットとデメリット。
クラウド化するにあたり、活用できる補助金について覗いてみましょう!
今さら聞けないクラウド化って?
クラウドってそもそも何?という方は意外と多いのではないでしょうか。
クラウドとは、「クラウドコンピューティング」の略で、インターネットを介して、ネットワーク、ストレージ、サーバ、アプリケーションなどのサービスを提供する利用形態のことです。
なぜクラウド(雲)なのか?は、ITエンジニアがシステムの設計図を描く際にインターネットを雲で表現することが多いという説もあります。
インターネットを介するサービス、インターネットの向こう側のシステムから提供されるサービスという意味で“クラウド”と呼ばれてます。
身近な例としては、Yahoo!メール、GoogleDrive、iCloudなどです
クラウドサービスの種類には色々なものがありますが、基本的には“インターネットを介して提供されている”と覚えておきましょう。
業務がはかどるクラウド化5つのメリット
1.コストが抑えられる
クラウド化には特別な機材の導入やシステムの開発は必要ありません。サービスに申し込むだけですぐに利用が可能で、イニシャルコストを抑えられる点が大きなメリットです。
自社でサーバーを保有すると、それなりのイニシャルコストが発生します。専門スキルを持つ担当者も配置しなければなりません。担当者がいない、または育っていない場合は外部に委託せざるを得ず、ランニングコストがかかります。クラウドサービスなら、費用負担は基本的に定額料金のみです。
2.サービス利用の場所を選ばない
場所を問わずに運用できるのもクラウド化の魅力です。自社サーバーの場合、特別な運用をしていない限り、オフィス外からはアクセスできません。その点、クラウドはインターネットを経由するため、遠隔地にいてもオフィスと同様にアクセス可能です。
社会情勢の変化により、リモートワークが増えている現状を考えると、場所を選ばずに利用できるのは大きなメリットと言えるでしょう。従業員は無理に出社する必要がなくなるため、経費削減の効果も期待できます。
3.運用負荷を削減できる
自社サーバーを運用する場合、サーバーを維持するための専任スタッフを置く必要があります。安定性やセキュリティ面の確保など、システム維持のためにかかる負担は軽いものではありません。
一方、クラウドサービスなら運用を任せきりにできるのがメリットです。従来は自社で行っていた細かなメンテナンスは、サービスの提供元が済ませてくれるので必要ありません。システムの維持に担当者を配置する必要すらなくなるため、人件費の削減につながります。
4.すぐにサービスを利用できる
クラウドサービスは既製品のシステムを購入する形になるため、契約後すぐに利用できるのがメリットです。自社でシステムを開発するとなると、利用開始までに数か月間かかることも珍しくありません。
ビジネスにおいてスピードは重要ですから、この差は大きいと言えるでしょう。速やかに社内システムを見直す必要があるときは、なおさらクラウド化を進めることをおすすめします。
5.データ共有が楽になる
クラウドサービスは、さまざまな端末に対応しているのも特徴です。パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットからもアクセスできるので、外出先から資料を確認したり、別の場所にいるスタッフに共有したりすることも簡単にできます。
サービスによっては共同編集といった作業も可能です。端末の環境が異なる場合でも、クラウドサービスにさえ対応していれば問題ありません。互換性を気にせず快適に仕事ができるようになるのは大きなメリットでしょう。
クラウド化3つのデメリット
クラウド化にはどんなデメリットがあるのでしょうか。
クラウド化のデメリット1.カスタマイズに制限がある
システムを自社で運用する形なら、社内の用途に合わせて自由にカスタマイズできます。
しかし、外部サービスを利用する場合は、あらかじめ決められた仕様やポリシーのなかでしか運用できません。
そのため、クラウド化を進める際には、実際にサービスを利用する社員の意見を吸い上げ、できるだけ自社の使い方にマッチしたサービスを選ぶのが重要です。
クラウド事業者のなかには、サービスを無料で利用できるトライアル期間を設けているところもあるので、本格導入する前に、小規模でテスト運用して使用感を確かめるのもおすすめです。
同時に、利用者が増減した場合の拡張性も意識してサービスを選ぶと良いでしょう。
対策:プライベートクラウドを選ぶ
構築や運用の手間が多少かかっても、使い方の自由度を優先したい場合は、プライベートクラウドを選ぶのも一つの手です。
プライベートクラウドなら、自社のポリシーや社内事情の変化に合わせて自由にカスタマイズできます。
外部サービスと異なり、社内から追加機能の要望があった際にも柔軟に対応できます。
クラウド化のデメリット2.システムの影響を受ける
自社で運用するより高い安定性が期待できるものの、クラウドサービスも完璧ではありません。
システム障害により業務がストップしてしまう可能性も考えられます。さらに復旧までの時間が長引いた場合は、大きな損害につながることもあるでしょう。
クラウド事業者側のミスで、自社の重要データが消失してしまう可能性もゼロではありません。
また、クラウド事業者の経営状況によっては、サービスが終了することも想定されるリスクの一つです。
対策:定期的にバックアップを行う
万が一のリスクに備え、定期的にデータのバックアップをとっておくことが重要です。
システム障害が発生しても、被害を最小限に抑えられます。
また、サービスが機能しなくなった場合の代替手段をあらかじめ考えておくと良いでしょう。
クラウド化のデメリット3.リソースやスキルが必要
オンプレミスに比べると運用負荷は軽減するものの、クラウドサービスを利用する場合においても、一定以上のリソースやスキルは必要です。
例えば、システムを導入するにあたって、各サービスの仕様をきちんと理解し、比較・検討をしたうえで、自社の要件に合ったものを見極める必要があります。
また、初期設定の手間がかかることに加え、社内の用途に合わせてカスタマイズする場合は、ある程度の知識がないと難しいでしょう。
対策:支援サービスを活用する
リソースの確保や、知識がある人をすぐに見つけるのは簡単ではありません。
そこで役に立つのが、オンラインアシスタントサービスです。
各分野におけるプロフェッショナルが、クラウド化にともない発生する事務作業を代行してくれます。
クラウド化に使える補助金オススメ3選!!
※2021年8月時点
国がデジタル化、クラウド化を推奨しているので、色々な補助金が出ているのですよ!!
1.IT導入補助金
2021年IT導入補助金は最大450万円費用補助を補助!
●業務ソフトウエア(クラウドの使用料は1年分)
●導入設置費用
●データコンバート費用
●導入指導費用
●保守費用(1年分)
クラウドのソフトウェア以外にも導入設置に関わるその他費用も対象となります。
詳細についてはこちらの記事をご確認ください↓↓↓
2.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ものづくり補助金は中小企業が経営革新のための設備投資等に使える補助金です。
一般型は上限1,000万円の補助。
補助率は1/2もしくは低感染リスク型ビジネス枠・小規模事業者で 2/3の補助が受けられます。
補助対象経費にクラウドサービス利用費が含まれております。
補助対象経費
機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費(グローバル展開型のみ)、広告宣伝・販売促進費(低感染リスク型ビジネス枠のみ)
3.事業再構築補助金
補助金額が100万円~1億円。補助率が1/2~3/4と、過去に類をみない大型の補助金です!
設備投資などの取り組み費用の最大2/3(上限1億円)、緊急事態宣言特別枠では最大3/4(従業員数に応じて上限500万円~1,500万円)が補助されます。
補助対象経費
建物費、建物改修費、賃貸物件等の原状回復、設備費、システム購入費、外注費(加工、設計等)、研修費(教育訓練費等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)等
詳細についてはこちらの記事をご確認ください↓↓↓
業務がはかどる「クラウド化」に「補助金」を活用しましょう!
行政は積極的な企業を応援していますよ!